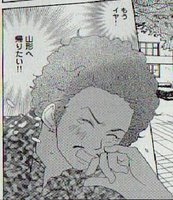正直、困ったちゃんな演奏だった。
今週水曜の都響定期、指揮者ジャン・フルネの引退コンサートのことだ。
そのときの概要は
「ぶらあぼ」のサイトに書いたけど、これはあくまでもニュースとしての記事。
そんで、オマエは個人的にどう感じたか、と聞かれれば、冒頭の「困ったちゃんな演奏だった」と答えるしかないのである。
そのコンサートは演奏会というよりも、完全にセレモニーでしかなったからである。
いや、コンサートとは一種のセレモニーなのであるから、今回はセレモニー的要素がなければ演奏そのものが存在しなかった、と言い換えたほうがいいかもしれないけど。
この日の演奏は録画され、DVD化されるという。その前にNHKの芸術劇場でも放送されるらしい。
やめたほうがいいのに、と思う。
演奏は記録したものでも楽しめることがあるが、セレモニーはその場に参列した者でないと、その意味を心から享受することはできない。
果たして、「フルネの引退コンサート」というセレモニーに立ち会っているという興奮を除外してこの演奏を聴いた場合、人々は何と感じるだろうか。
フルネの演奏を知らない人が視聴すれば、彼がこんな程度の指揮者だと思ってしまうだろう。
そういう演奏会だったのである。
だいたい、演奏開始前の場内アナウンス、「二度とないフルネ氏の引退公演を皆さんで楽しんでいただけますよう、ご協力をお願いします」って、いったい何なのよ。
「二度とない」のは、どのコンサートでも同じ。わたしはそのアナウンスを聞いて、ちょっと不安になった。演奏がボロボロだけど(すんまへんすんまへん)、記念すべきコンサートなのだから(みなさんはそのへんわかってるでしょ?)、文句言わずに楽しめよ(同じアホなら踊らにゃソンソン)、といっているように聞こえたからだ。
前半はまったくノレなかった。
ベルリオーズの《ローマの謝肉祭》は、直線的でいかにもフルネのアプローチだな、とは思ったけれど、あまりにもオーケストラの反応が良くない。リズムが眠そうで、これがフルネの演奏なのか、と悲しい気分になる。いかにもフルネらしい解釈だったから、その詰めの甘さが気になってしまうのである。
二曲目、伊藤恵をソリストに迎えたモーツァルトは、遅いだけのユルユルな演奏に終始。
どうもこの人のピアノが好きじゃない。以前、同じ組み合わせでラヴェルの協奏曲を聴いたことがあるが、第2楽章冒頭のソロをあまりにも無関心・無感動に弾いていたので、アレ? 何かあったのかしら、と心配になったものだ。この日も同様、ベッタリ音で、音と音のつながりを無視したように弾く。
もちろん、「表情なんかつけてやんないゼ」という表情さえない。そういうものは、もう「無私」の境地とお呼びして、崇め奉るしかないだろう。
休憩を挟んで、メイン・プログラムはブラームスの交響曲第2番。定評が高いショーソンとかルーセルの交響曲で締めて欲しかったのだけど、フルネは心底ドイツものが好きなのだ。
テンポは遅く、薄明の美が漂わせながら、曲が始まる。第1楽章展開部も終わるあたりから、オーケストラの音も立ってきて、やっと音楽が立体的になってくる。
問題は、オーケストラはフルネの棒で演奏していないということだ。振り間違いも多い。コンサートマスターの身振りが次第に大きくなるのがよくわかる。
音楽はぶくぶくと大きくなり、空中分解しそうになる不安定さに、わたしはドキドキしてしまったものだ。オーケストラも必死だったろう。
往年のフルネは、ノリが悪い都響をよく引っ張っていたものだ。インバルやベルティーニよりも相性が良かったと思う。
そういう指揮者の最後の演奏なのだから、オーケストラは必死こいて指揮者の解釈について行く可能性もあるんじゃないか、なんて甘い考えもあった(クルト・ザンデルリンクの引退コンサートのように)。しかし、それは彼らのここ何年かの演奏を聴いていれば、そんなことは起こらないのは明白だった。
ついて行かせるだけのモノをフルネはすでに失っていたからだ。
テンポは緩慢になり、彼の持ち前の造形感覚はフルネにはもう無かった。
今、オーケストラが必死こいてるのは、「指揮者の〝間違った〟解釈に、いかについていかないようにするか」という命題に対してなのだ。敬愛していた指揮者の最後の演奏会をつつがなく終わらせるためにも。
ブラームスの第4楽章は、演奏者、そして聴き手の様々な思いが交錯するような、「壮大」な音楽になった。
あーあB級だな、と思いながらも、オーケストラの明るい響きに浸っているうちに、何かしら暖かい感情が湧いてくるのだった。
これが、まさに「92歳の指揮者の最後の仕事」に接しているという、セレモニー効果なのだろう。
演奏直後には、不思議に心を動かされたものだ。
演奏そのものは評価できなかったとハッキリ言えるけれど、まんまとセレモニーのオーラにやられちまった、ということだ。そこが、「演奏」が聴きたかった自分としては「困ったちゃん」なんだよな。うぷっ。